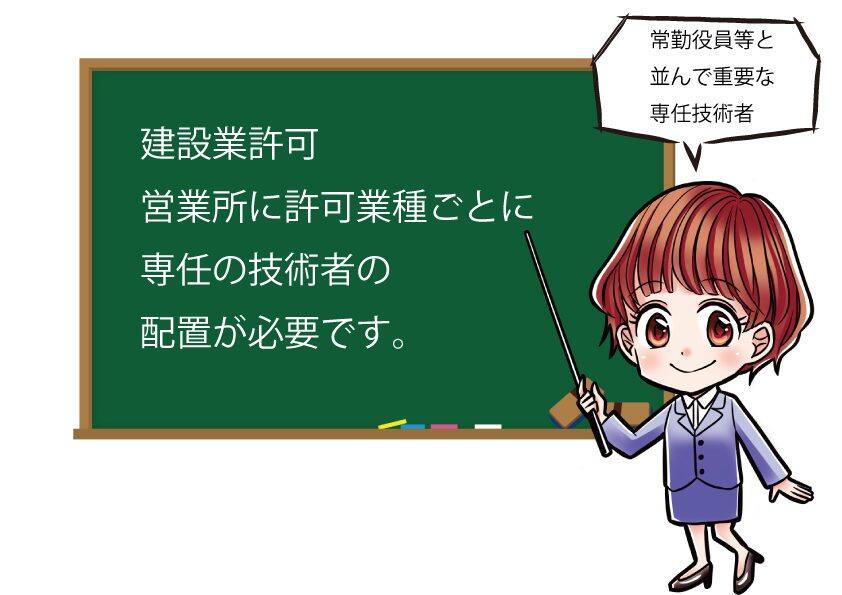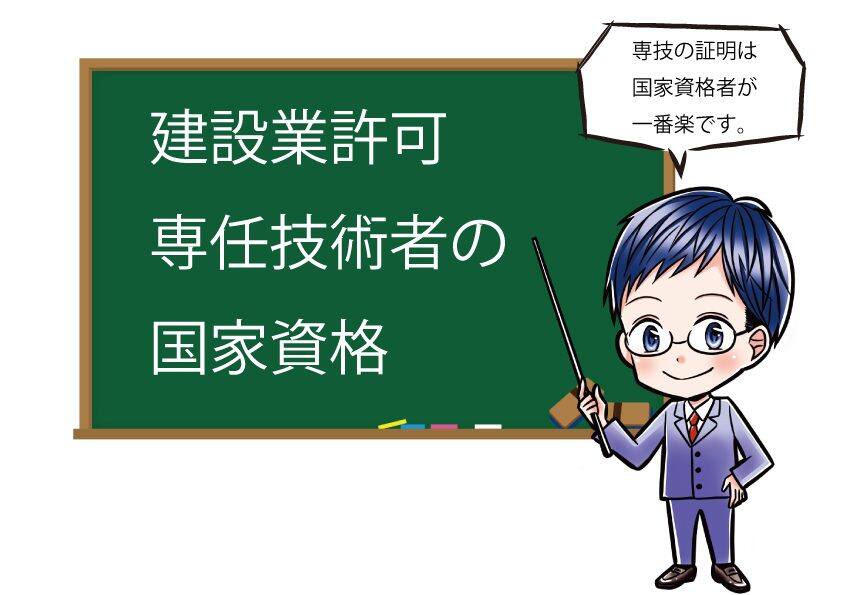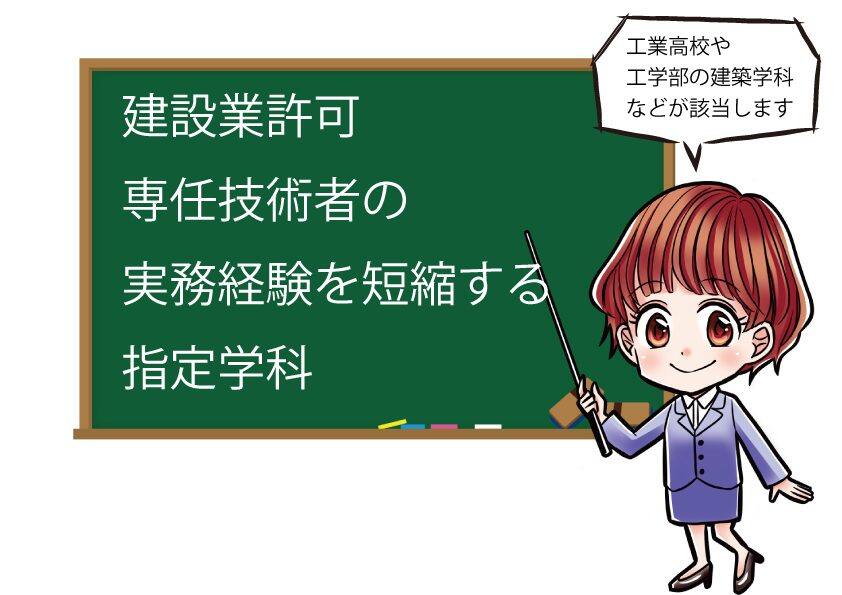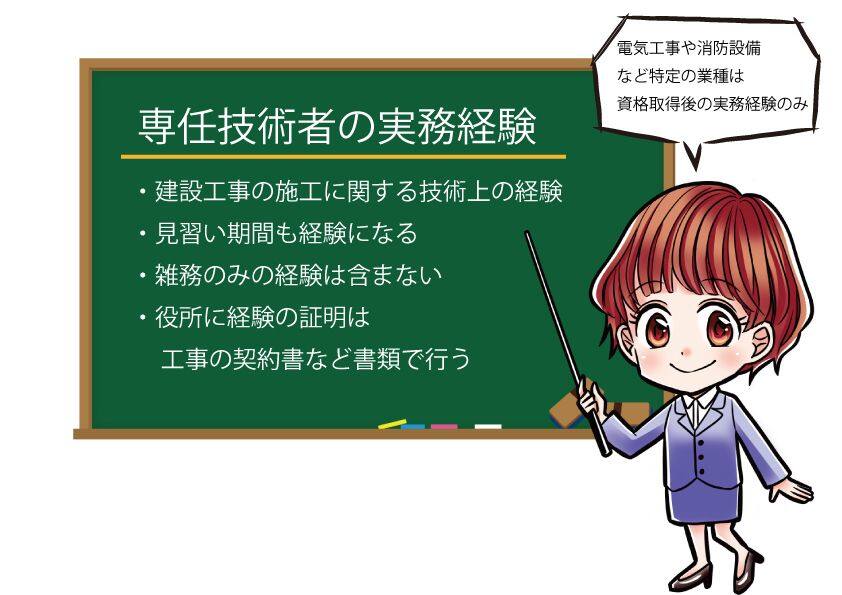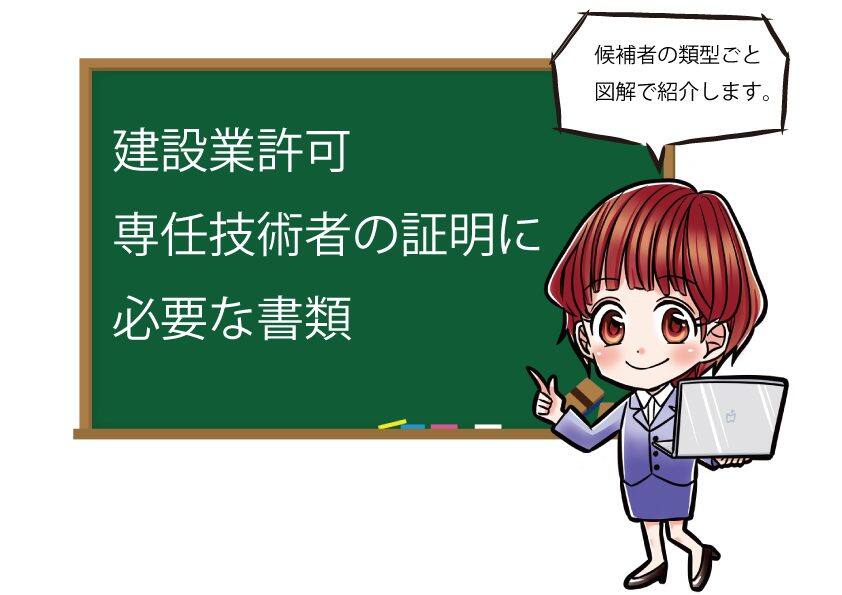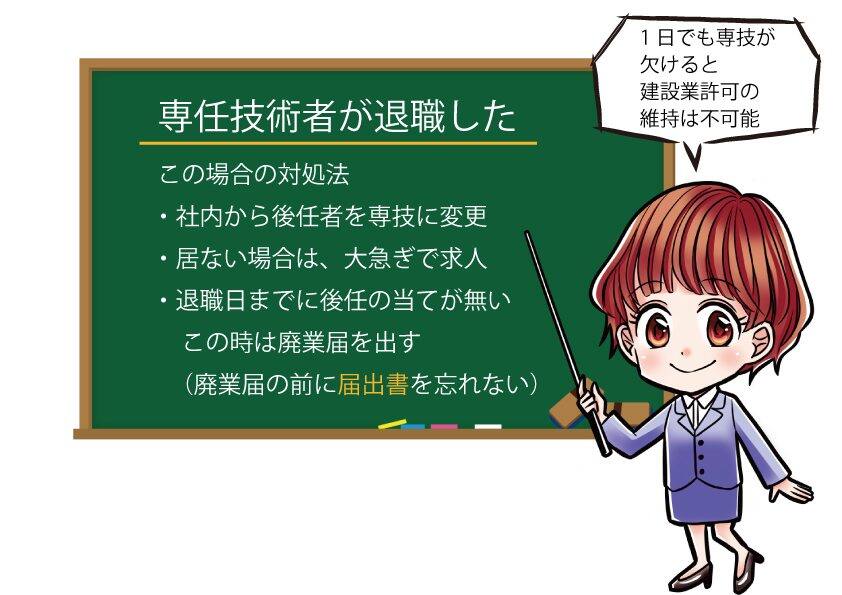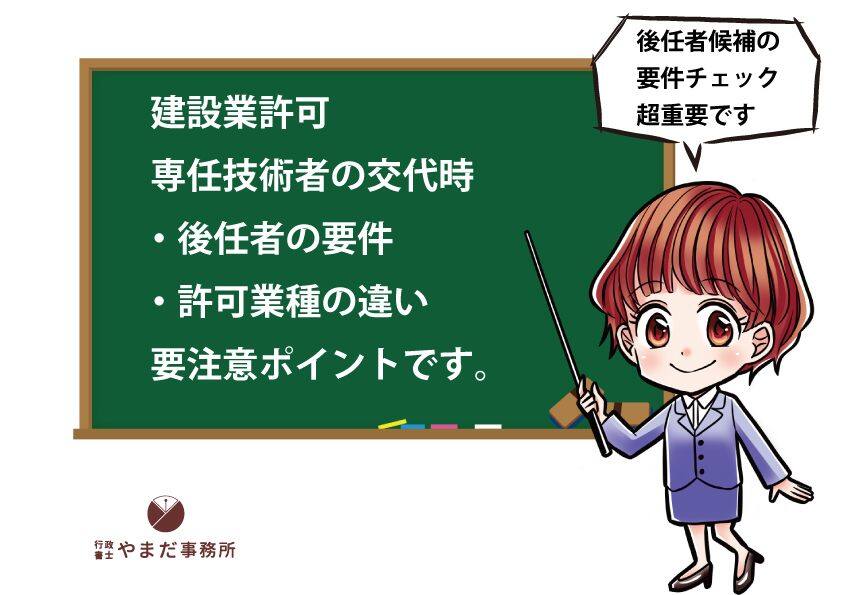建設業許可の大臣認定とは
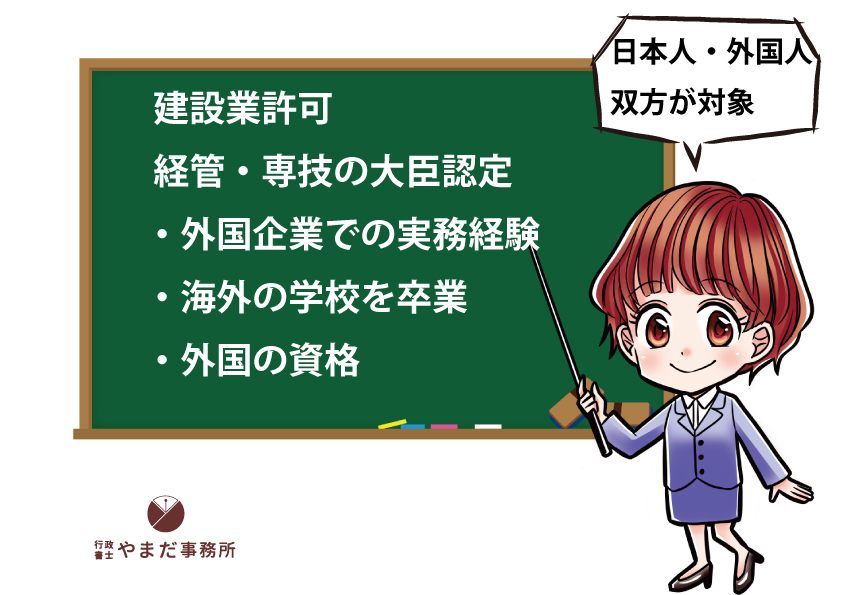
この記事は建設業許可の国土交通大臣認定について。
正確には「建設業に関する外国での経験等を有する者の認定」となりますが,長いのでこの記事では「大臣認定」で統一します.
大臣認定とは海外での実務経験や資格で,常勤役員等(経管)や専任技術者(営業所技術者等)になれるかを確認するための手続きです.
- 外国の企業での経営経験や実務経験
- 海外の学校の卒業資格(大学や短大,専門学校)
- 外国の資格(Architect)等
ここで言う外国の企業は日本にある外資系企業ではありません.
外資系企業は普通の実務経験になります.
(日本企業の注文書などがあるため)
経営経験は日本法人か日本支店かで証明方法が変わってきます.
2024年に法律が改正されて、専任技術者の名称が営業所技術者等になっています。
呼び方が変わっただけで役割も要件も同じです。
最も役所の担当官を含め専技と呼びますが…
外国企業で海外での経験や外国の大学などが対象です.
- アメリカの建設会社での取締役経験.
- スペインの会社でSagrada Família(サグラダファミリア)の建築工事をしていた経験.
- ミャンマーのタンリン工科大学(Technological University Thanlyin)の卒業資格.
- ベトナムの建築士(Registered Architect)の資格を持っている.
上記の様な経歴や資格は,建設業許可の要件を満たしているか判断が難しいです.
もともと日本の建設業許可の制度は,日本国内のみを対象としていました.
日本企業での役員経験や工事の経験,日本の学校,国家資格.
外国企業の海外での経験や学歴資格は想定されていませんでした.
上記の経験や資格で建設業許可を取れる様にするのが,国土交通省の大臣認定になります.
大臣認定の対象は日本人と外国人
海外の大学を卒業した帰国子女や向こうで働いていた日本人で.
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務(技人国))で働く外国籍の人.
経営管理ビザで建設業を営む人や役員が常勤役員等(経管)になる.
この様な方を想定しているのだと思います.
身分系ビザ(配偶者ビザ・定住者)や永住者以外の外国人を常勤役員等や専任技術者にする場合,在留資格の該当性なども考慮する必要があります.
技人国ビザや経営管理ビザは,現場作業が出来ないので注意が必要です.
工事経歴書の主任技術者欄に,該当する方の名前があると資格外活動になる可能性があります
(特に少額の工事だと現場作業していると入管に判断される可能性あり)
大臣認定の申請先は霞が関にある本省
大臣認定は,地方整備局や都道府県庁ではできない手続きです.
東京にある国土交通省不動産・建設経済局国際市場課国際調査係です.
(漢字だらけで長い部署名です…)
建設業許可の大臣認定の流れ

ここからは大臣認定の流れをご紹介します.
上記の画像は国土交通省の資料から弊所の行政書士が書き起こしたものです.
参考;建設業に関する外国での経験等を有する者の認定について(大臣認定)
①申請書類の準備
まずは国土交通省のサイトに書かれた必要書類を集めます.
認定申請書や履歴書に常勤役員等証明書,実務経験証明書など.
外国の資料(契約書や卒業証明書)は日本語に翻訳します.
和訳は必要な個所だけされていればOKです.
(全文翻訳する必要はありません)
審査項目は申請者の外国の部分だけではなく,常勤役員等(経管)や専任技術者の要件を満たしているかまでチェックされます.
なので提出書類は,日本での経験や学歴,資格証なども一緒に必要です.
②担当官署と事前相談
書類が一通り完成したら,国土交通省の国際調査係に電話します.
申請者の状況を説明し,作成した資料一式を提出します.
提出した資料を担当者がチェック.
③国土交通省の確認終了
担当官のチェックで問題あれば,問題点を潰した書類を提出します.
おそらく個別の追加資料を求められると思われます.
問題なければ,次の工程に進みます.
④外国語の資料の翻訳文の公証
外国の資料(契約書や卒業証明書,資格証)の和訳文を公証します.
これは公証役場で行います.
やり方は①私署証書の認証か②宣誓認証の2種類あります.
作成した書類が作成者本人の意思に基づいて作成された物と公証人が認証することで公的な信用を付与するもの.
詳しくは法務省のサイトをご確認ください.
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji30.html
⑤本申請
翻訳文の認証が終わったら,書類一式を完成させます.
完成した書類を提出します.
これが本申請になります.
⑥⑦国土交通省の審査
提出された申請書の中身を審査します.
審査が完了して,合格の場合は認証証が送付されます.
ここまでが建設業許可の大臣認証になります.
⑧⑨認定証の受領と建設業許可申請
次は建設業許可申請に入ります.
都道府県庁や地方整備局が指定する書類と認定証を提出します.
書類受理後,知事許可の場合は受理から1か月,大臣許可の場合は120日で許可通知が届きます.
大臣認定の必要書類
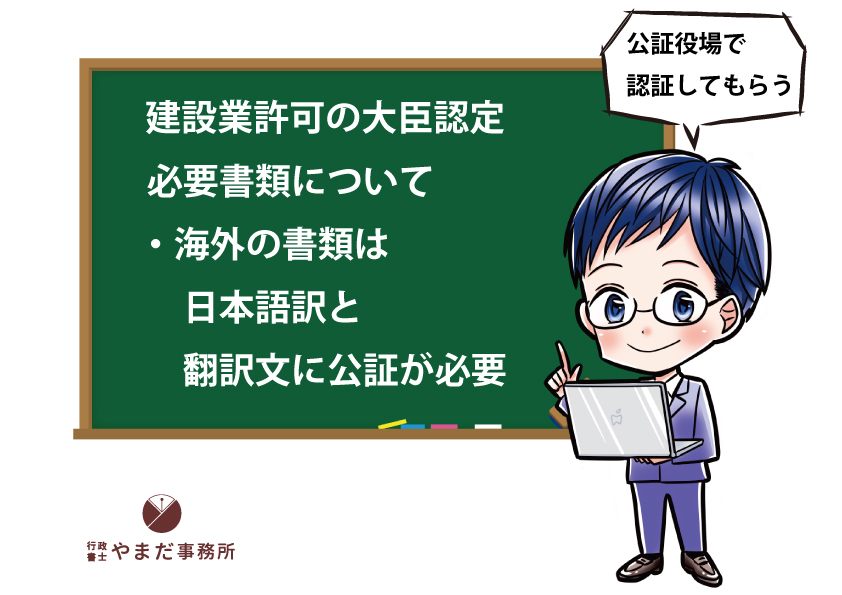
ここからは大臣認定で必要な書類をご紹介します.
ここに挙げられた書類の他に役所から追加資料が求められる可能性があります.
あと日本での経験と外国の経験の両方で経管や専技になる場合は,日本の資料(契約書など)も一緒に提出します.
常勤役員等の大臣認定の必要書類
こちらは1人で常勤役員になる場合の必要書類です.
- 建設業の役員経験5年以上.
- 建設業の準ずる地位の経験5年以上
- 建設業の補佐経験6年以上
上記の経験を証明する場合の必要書類になります.
- 認定申請書(別紙様式1)
- 履歴書(常勤役員等の略歴書の使用可能)
- 常勤役員等証明書(建設業許可の書類)
- 役員就任・退任議事録or会社登記簿謄本
- 会社組織図
- 建設工事を施工した契約書のコピー(1年に1枚程度)
- 会社概要資料(パンフレット,建設業許可証の写し,会社の謄本など)
チームで経管になる場合の大臣認定の必要書類
次はチームで常勤役員等になる場合について.
- 建設業の役員2年以上+5年以上の財務・労務・業務の経験
- 5年以上の役員経験&その内2年は建設業の役員経験
- 5年以上の財務・労務・業務の補佐を配置
上記の要件を満たしたチームで経管になる場合の大臣認定の書類は以下の通りです.
- 認定申請書(別紙様式1)
- 履歴書(役員と補佐)で常勤役員等の略歴書の使用可能
- 常勤役員等の証明書(建設業許可の書類)
- 直接に補佐するものの証明書( 〃 )
- 役員就任・退任議事録or会社登記簿謄本
- 補佐人に対する確認資料(会社組織図,人事発令など)
- 建設工事の契約書の写し(1年に1枚程度)
- 建設業許可の許可証(許可業者)
- 会社概要資料(パンフレット,建設業許可証の写し,会社の謄本など)
一般建設業許可の専任技術者の大臣認定
次は専任技術者の必要書類です.
まずは一般建設業許可の場合です.
- 指定学科(工学系大学・短大・高校)の卒業資格
- 大学・短大卒業:3年以上の実務経験
- 高校卒業:5年に実務経験
- その他:10年以上の実務経験
上記の要件を証明する場合です.
- 認定申請書
- 認定を受ける人の履歴書
- 卒業証明書+履修証明(関連学科)
- 実務経験証明書(建設業許可の書類)
- 工事契約書のコピー,発注者の証明書
- 会社概要資料(パンフレット,建設業許可証の写し,会社の謄本など)
一般建設業の専技,国家資格の大臣認定
次は建築士(Architect)などの資格で専任技術者を証明する場合です.
- 認定申請書
- 認定を受ける人の履歴書
- 卒業証明書+履修証明(関連学科)
- 技術資格者証の写し
- 資格取得の要件を確認する資料
- 会社概要資料(パンフレット,建設業許可証の写し,会社の謄本など)
外国の資格が日本の国家資格と同等であるかを確認する必要あります.
資格の受験資格や合格基準,試験の内容が分かる資料が必要になります.
特定建設業許可の専技,国家資格での大臣認定
次は特定建設業許可での専任技術者の場合です.
まずは国家資格から.
- 1級の施工管理技士
- 国家資格+2年以上の指導監督的実務経験
上記のいずれかを証明する必要があり,一般建設業許可よりハードルが高くなります.
- 認定申請書
- 認定を受ける人の履歴書(関連学科)
- 技術資格者証の写し
- 資格取得の要件を確認する資料
- 指導監督的実務経験証明書(建設業許可の書類)
- 指導監督的実務経験を積んだ工事契約書のコピー,体制図など
- 工事金額の円レートの計算を確認する資料
- 会社概要資料(パンフレット,建設業許可証の写し,会社の謄本など)
指導監督的実務経験は,日本円で4500万円以上の工事を技術面を総合的に指導監督した経験.
為替レートは工事当時の物を用い,当時の円レートやレート表.
円レートを計算した計算式の提出も必要.
特定許可の専技,実務経験の大臣認定
ラストは特定建設業で国家資格以外での専任技術者の場合です.
- 一般建設業許可の専任技術者
- 2年以上の指導監督的実務経験
国家資格以外の場合は,上記2点を満たす必要あり.
建築一式,土木一式,管工事,鋼構造物工事,舗装工事,電気工事,造園工事の7業種は1級の国家資格者のみ.
- 認定申請書
- 認定を受ける人の履歴書(関連学科)
- 指導監督的実務経験証明書(建設業許可の書類)
- 指導監督的実務経験を積んだ工事契約書のコピー,体制図など
- 工事金額の円レートの計算を確認する資料
- 実務経験証明書(建設業許可の書類)
- 実務経験を証明する工事契約書のコピー(1年に1枚程度)
- 会社概要資料(パンフレット,建設業許可証の写し,会社の謄本など)
以上が大臣認定の確認資料です.
大臣認定は個別的な手続き
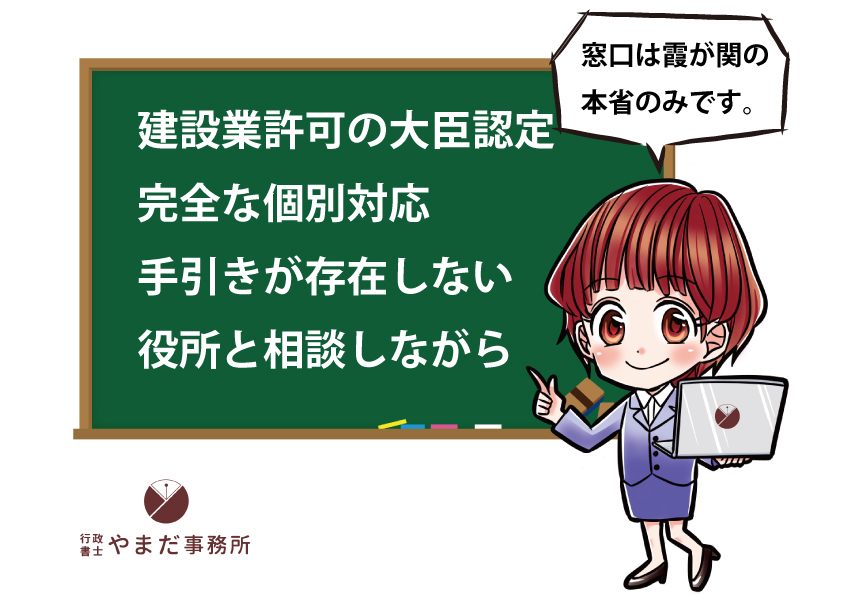
最後に大臣認定の特徴をご紹介します.
この手続きには建設業許可の手引きのようなマニュアルが存在しません.
1件1件,国交省の担当者が調べていく性質のものです.
公表されているのは,受付窓口と最低限の資料のみ.
基本的な進め方は,国交省国際調査係の担当者と相談しながらとなります.
また1件1件が状況が異なるので,認定手続きに必要な時間や許可の見込みが読めない代物です.
この様に大臣認定は,非常に大変な手続きではあります.
しかしながら外国の経験や学歴,国家資格で建設業許可を取る唯一の道でもあります.
ここまでお読みいただきありがとうございます.
この記事を書いた人

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
大阪府行政書士会 法人研究会会員
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪商工会議所 建設・建材部所属
建設業経理士2級
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。
産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。
年間相談件数は、500件を超える。
【表彰】

【運営サイト】